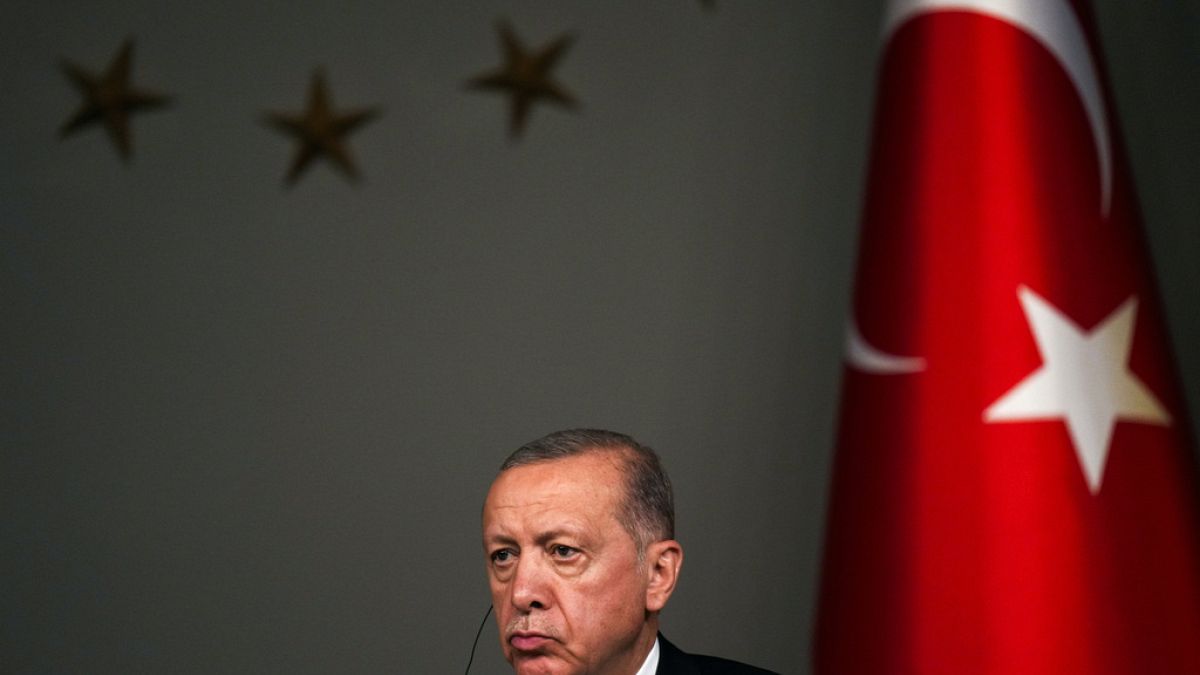ベルトコンベア道路は、日本が温室効果ガス排出とトラック運転手不足という2つの問題に同時に取り組むのに役立つ可能性がある。
東京-大阪間の500キロ路線の最新計画が先月、国土交通省(国土交通省)によって発表された。
高速道路の真ん中を走るベルトの上や路肩に沿って、あるいは地下トンネルを通って、自動化された無人電気自動車で物品が輸送されている様子が示されています。
24 時間稼働する「Autoflow-Road」は、1 日あたり 25,000 台のトラックと同じ量の貨物を運ぶことができます。
読売新聞の試算によれば、10キロメートルあたり最大800億円(5億1,200万ユーロ)の費用がかかり、10年以内に稼働する可能性があるという。
日本のドライバー不足は環境に明るい兆しをもたらす可能性がある
国土交通省は、提案されている自動化道路は、道路スペースを最大限に活用しながら「物流危機に対応し、温室効果ガスを削減する」としている。
このプロジェクトの主な目標は、日本の悪化に取り組むことです。トラック運転手この不足は、国の人口高齢化が急速に進んでいることと、低賃金と長時間労働で知られる業界への参入を若者が躊躇していることによって拍車がかかっている。
ドライバーに認められる時間外労働の量を削減する新たな規則が、配達の遅れに拍車をかけている。
これは特に問題となる生鮮食品イチゴや白菜などは、収穫したらすぐに輸送する必要があり、輸送しないと無駄になったり価値が下がったりする危険があります。
現在、日本の貨物の90パーセント以上は陸路で輸送されています。
野村総合研究所による最近の調査では、2030年までに35%の資源が不足することが示唆されています。トラック運転手日本全国の輸送貨物量と比較して、農村部が最も大きな打撃を受けるだろう。
はるかに大きなスケールではありますが、鉱山で使用されている既存のベルトコンベア システムをモデルにすることができます。
貨物輸送による二酸化炭素への影響は何ですか?
国際輸送フォーラム (ITF) は、貿易関連の貨物輸送が世界の総 CO2 排出量の 7% 以上を占め、全体の約 30% を占めていると推定しています。輸送関連の排出。
米国、中国、EUがトップエミッター国際エネルギー機関 (IEA) のデータによると、陸上貨物輸送では日本が約 3% を占めています。
日本は温室効果ガス削減を目指す排出量2030 年までに 46% 減少します。
重量車両、長時間、長距離の貨物輸送は、業界が利用することを困難にしています。電気自動車(EV)短距離路線や小型トラック向けに一部の企業が導入しています。
日本の新幹線の利用、トラックと貨物輸送の組み合わせなど、貨物輸送を脱炭素化する他の方法配送効率化なども試行中です。