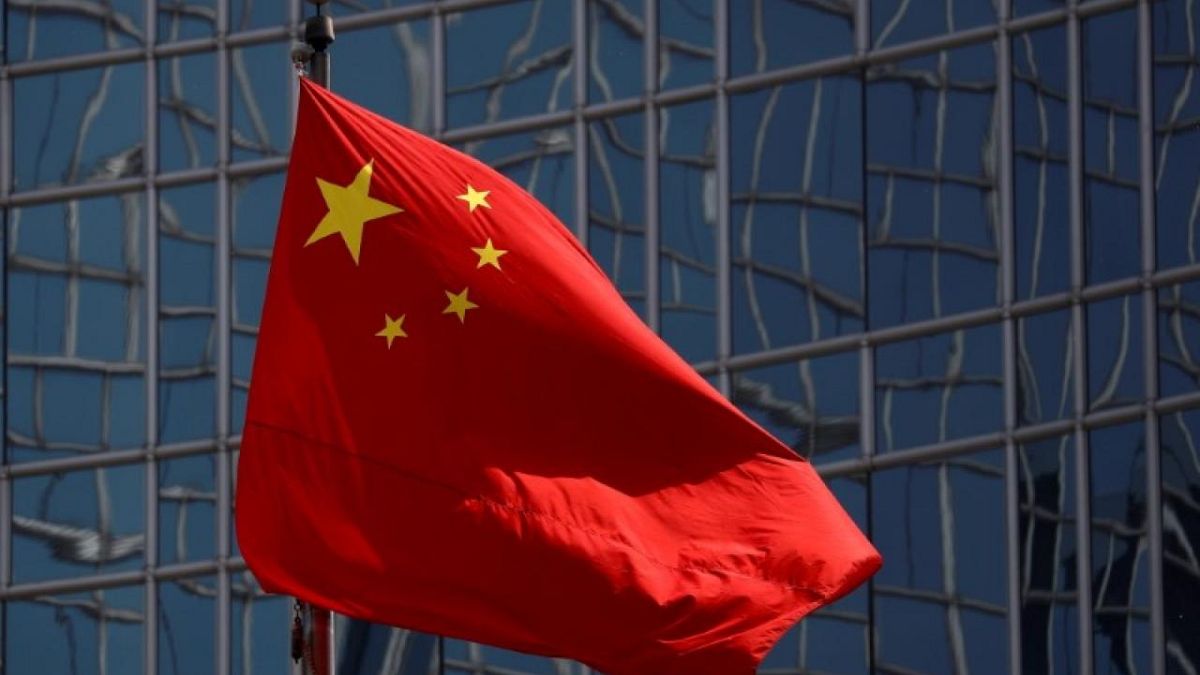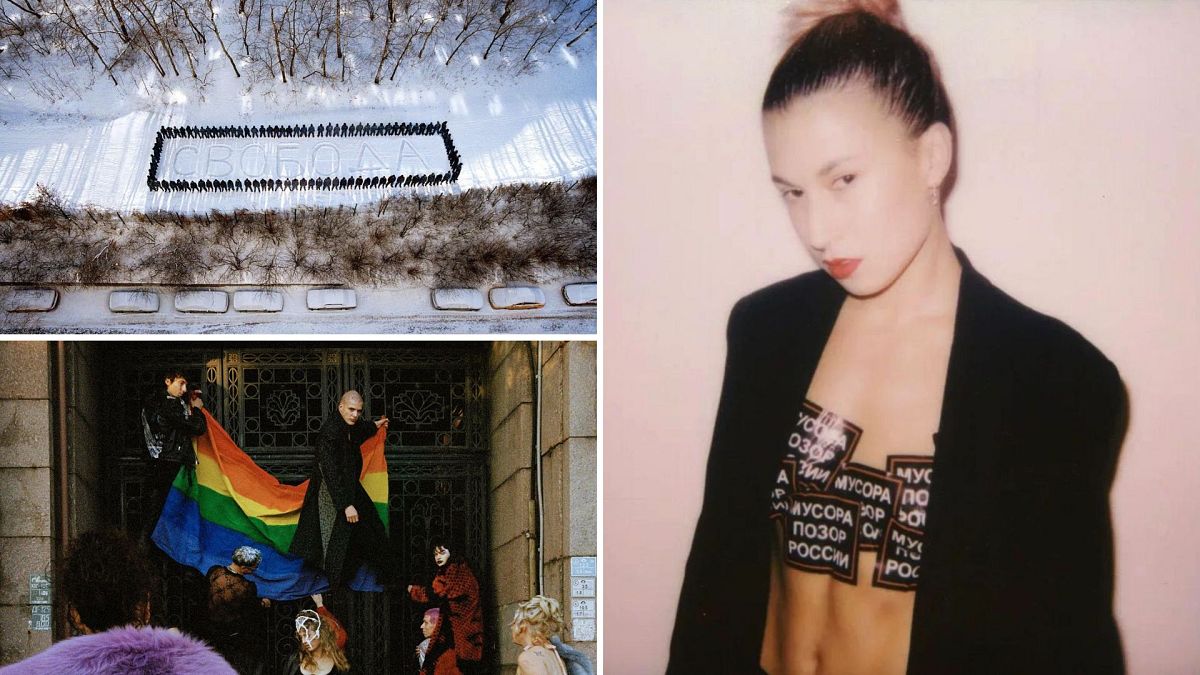フランスのエマニュエル・マクロン大統領が就任してから約3週間が経ちました。彼の政府は非常に議論の多い年金改革案を議会を通じて強行させた、憲法の抜け穴を使って投票を回避する。
この動きはさらなる抗議活動を引き起こし、デモは以前よりも暴力的な性格を帯びた。
しかし、マクロン氏の年金法と同氏の憲法利用に対するこうした抗議活動が、フランス第5共和制に劇的な変化をもたらす可能性はあるのだろうか?そんなに早くはない、と憲法専門家は主張する。
「政権危機を超えた政治危機」
パリ・ナンテール大学で公法講師を務めるティボー・ムリエ氏にとって、今日の年金抗議活動は単なる政治的危機ではなく、憲法上のより大きな危機ではない。
「当分の間、第5共和制はこの衝撃を乗り切るだろう…とはいえ、より広範な制度的危機になる可能性はある」と憲法専門家は語った。
それは、より暴力的な暴動を引き起こした重要な要素の一つが、政府が投票なしで議会を通じて改革を強行することを可能にする憲法第49条3項をマクロン氏が利用したことだったからである。
この条項は合法であり、広く使用されているが、2008年のフランスの制度改革の対象となり、その使用は予算法、社会保障財政、または同じ議会で提案された他の法案に限定された。
また、この条項の使用後に国会議員が不信任投票を発動することも認められており、野党議員が実行したが、国会または下院での可決にはわずか9票足りなかった。
マクロン大統領を「王様」のように振る舞っていると呼んだ抗議活動参加者にとって、この記事は、第5共和制がいかにして強力な大統領が反抗的な議会を無効にすることを容認しているかを示す一例となる。
これはフランスの制度に対する新しい批判ではありません。
アルジェリアの蜂起後、1958年にシャルル・ド・ゴール将軍の一部によって設立されたフランス第5共和制は、政府、議会、憲法評議会を掌握する行政府の役割について長年批判に直面してきた。
その後の共和国の変化により、大統領の影響力はさらに増大した。
1962年の国民投票では一般投票によって大統領が選出され、2000年の国民投票では大統領選挙と議会選挙の日程が一致し、ほぼ常に大統領の絶対多数が得られた。
しかしマクロン氏議会で絶対多数を失った昨年の再選直後で、これはフランスでは1988年以来初のことであり、これは理論的には大統領が野党ともっと交渉すべきであることを意味するとムリエ氏は言う。
「我々には絶対多数派を持っているかのように振る舞う政府と大統領がおり、大統領は(議会の)比較的従順な多数派を得て自らの計画を実行する『大統領主義的』慣行を続けることができるが、実際はそうではない」と述べた。 。
極左野党のマティアス・タベル議員はユーロニュースに対し、フランスはマクロン氏が選挙で絶対多数を失ったことを今頃発見したかのようだと語った。
「我が国はおそらく唯一の民主主義国家であり、いずれにせよ、共和国、政府の大統領が国会の投票なしに法律を制定できる唯一の国、ヨーロッパで唯一の国だ」と付け加えた。
歴史的に見て、フランス政府が退職金制度を改革しようとするたびに大規模な抗議活動を引き起こし、1995年にはデモによってアラン・ジュペ首相が改革からの撤回を余儀なくされた。
そして、抗議活動は依然として退職年齢を62歳から64歳に引き上げることに焦点を当てているが、ボルドー大学の公法講師カロリーナ・セルダ・グスマン氏は、今問題は大統領選挙が何を表し、何を表しているのかという問題でもあると言う。それが大統領に与える使命。
現在の年金危機が第六共和制をもたらす可能性はあるだろうか?
フランスの第5共和制は、70年間続いて第二次世界大戦中の1940年に終わった第3共和制に次いで2番目に長く続いている。
左翼政党アンソウミセ フランス(フランスは屈しなかった)昨年の大統領選挙の第1回投票で3位となったジャン=リュック・メランション党首の下、綱領に第6共和制の提案を盛り込んでいた。
同党のタベル議員はユーロニュースに対し、彼らの提案が今月のより大規模な左翼連合の議論の一部となることを期待していると述べ、同党の見解ではフランス政府は「民主主義の異常」であると付け加えた。
しかし、現在の危機は新共和国について「語るには良いベクトル」ではあるが、有権者はそれを求めていない、とムリエ氏は言う。さらに、同氏の見解では、2008年に実施されたような大規模な制度改革は法的に達成が難しく、それには「政治的意志」もほとんどない。
マクロン氏率いるルネサンス党のオルガ・ジベルネ議員は、先月報道陣に電子メールで送った声明で、第5共和政はフランスのさらなる安定をもたらしたものであり、「民主主義の逸脱」ではないと主張した。
同氏は、第49条3項の適用は美しくはないが、「治癒の可能性を残している」一方で、依然として「限界を示している」と述べた。
「国会議員の過半数が年金改革に賛成しているにもかかわらず、これは民主主義の否定とみなされます。これは少数派が何の疑問も持たずに自分たちが多数派であると主張する制度の皮肉です」と彼女は主張した。
チェルダ=グスマン氏は、憲法は建前上はバランスがとれているが、実際には「全く異なっており、大統領がすべての国政を掌握することを可能にしている」ため、第五共和制には確かに「裏切り」のようなものが存在すると指摘した。
「第49条3項を発動することを決めたのは大統領だが、それを実行するのは大統領の責任ではない。それは首相のはずだ」と彼女は語った。
さらに、国民が大統領に決定を押し付けることができる「出口」はほとんどなく、存在するものは国民投票や議会解散など大統領の手に委ねられたままである、とセルダグスマン氏は付け加えた。
しかし彼女は、フランスに第6共和制をもたらす条件はおそらく整っていないとしながらも、現在の危機は他の制度的変化につながる可能性があると述べた。
実際、マクロン氏は1期目にすでに憲法改正を試みており、議会選挙に比例投票を追加し、議員の数を削減する計画を立てていた。
同氏は「黄色いベスト運動」の後に、議会と国民が共同で住民投票を実施しやすくする改革を再度試みたが、法案は実現しなかった。
先月、共産主義国会議員ステファン・ペウ提案を出しました252人の国会議員が賛成票を投じて年金改革案を国民投票にかけるというものだ。この提案は現在、フランスの憲法評議会で検討されている。
今のところ、更なる抗議活動が計画されているため、退職改革案と国民投票について議会がどのような決定を下すかは待ちの勝負だ。
「もしかしたら、この危機は第五共和国の機能不全について議論する機会かもしれない。私たちは政治的にそれを行う必要があるが、それは野党だけでなく(大統領の)多数派からもたらされなければならないことを意味する」とムリエ氏は語った。