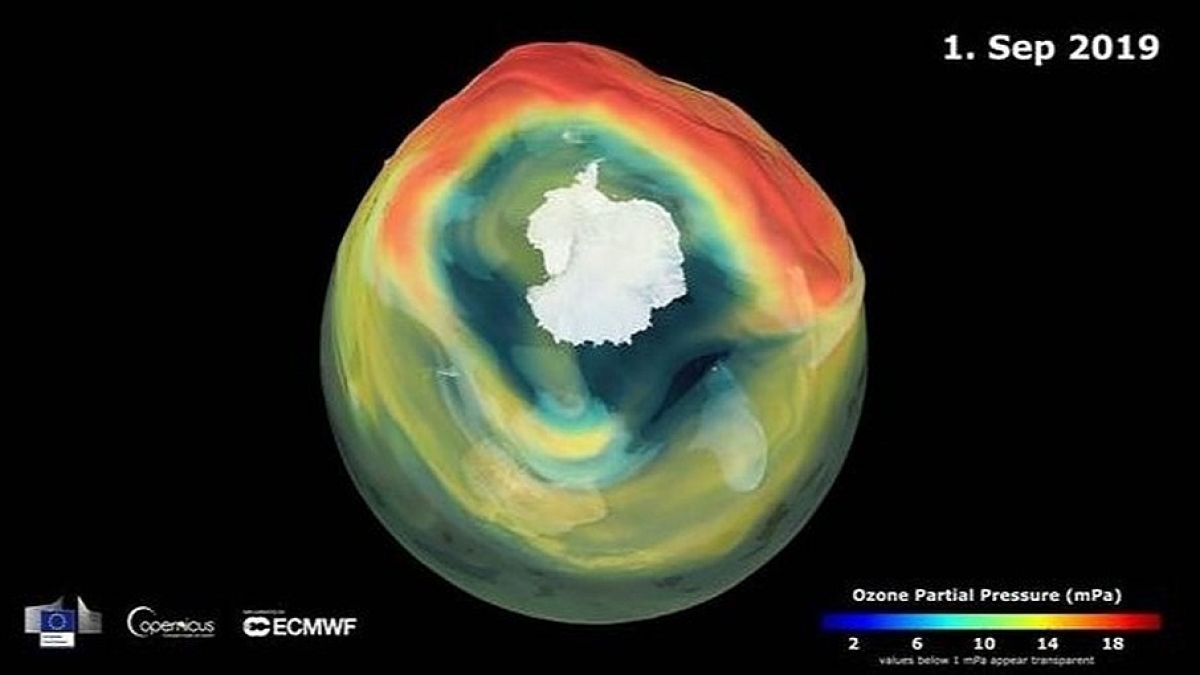「私たちはゆっくりと自分たちの物語と現実を取り戻し、語り直しています。」アーティストで作家のマレット・アン・サラは、芸術をこのように見ています。これは、植民地主義の主張が続くサーミ人の闘いにおける重要なツールです。
初心者にとって、これは予想外の発言かもしれません。北欧諸国は世界的な平和の実現者として、また民主主義と人権の分野における至極の標準として持ち上げられることが多いため、この地域における植民地占領と侵略の主張は不快に思えるかもしれない。
しかし、マレット・アンネ・サラと、アーティスト仲間のパウリナ・フョードロフとアンデシュ・スンナにとって、彼らは今後の芸術活動のバックボーンを形成しています。ヴェネチア・ビエンナーレ、今年は歴史的初となる、ノルディック・パビリオンの「」への変革が見られます。サーミ・パビリオン”。
「土地に起こることは、人々にも起こる。」
この変革は、先住民族サーミ族の文化と主権を祝うものであり、彼らの祖先の土地(サープミとして知られる)は、ノルウェー北部、スウェーデン、フィンランド、ロシアのコラ半島の広大な範囲に広がっています。
「私たちは自分たちを国境のない民族だと考えています」とマジャ・クリスティン・ジョーマは言います。ノルウェー・サーミ議会文化と風土を担当する評議員。 17 世紀の宣教師の到来による初期のキリスト教化に続き、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシアの政府は 19 世紀から 1960 年代まで積極的な同化政策を追求しました。その政策には寄宿学校の設立、サーミ語の抑圧、およびサーミ語の抑圧などが含まれていました。サーミ人を土地から追放すること。
サーミ館は、ノルウェーとフィンランドで北欧植民地主義に取り組む真実和解委員会が進行し、スウェーデンでも議論が行われており、重大な岐路に達している。
このような政策の正式な終了にもかかわらず、サラ、フョードロフ、スンナは、サーミの土地、習慣、言語を保存するための継続的な闘争を表明しているが、その線引き自体が、人々は土地と不可分であると考えるサーミの世界観とは異質である。
「自然と文化の間のこの西洋風の二重性は、サーミ人の観点からは意味がありません」と、この博物館のディレクター兼チーフキュレーターは説明します。ノルウェー現代美術局(OCA) のカティア・ガルシア=アントンは、「サーミ人の視点の核心は、『土地に起こることは、人々にも起こる』という一文に要約できる」と強調した。
「私たちが土地を大事にすれば、土地も私たちを大事にしてくれるでしょう」と共同キュレーターでドゥオジャール(サーミ人の語り部で知識保持者)のベアスカ・ニイラスはコメントする。
「生きたサーミ文化の鼓動」
サーミ人と北欧の視点の間の不協和音は、おそらく、トナカイ牧畜というサーミ人の伝統的な職業を維持するための戦いに最もよく表れている。
「政府はトナカイ放牧を生活様式ではなく経済として扱っています」とガルシア=アントンはコメントする。逆に、「トナカイの放牧は、生きたサーミ文化の鼓動を表しています」とサラは説明する。彼の作品は、国内法に基づく捕食動物の過保護(オオヤマネコやクズリの数の増加につながる)、強制的な飼育など、今日の遊牧民が直面している問題を呼び起こしている。伝統的なサーミの土地を通る古代のトナカイ移動ルートへの殺処分と風力タービンの設置。
サーミ議会の勧告は「民主主義における権力の幻想」に過ぎないとサラさんは信じているが、その勧告はほとんど無視されており、トナカイは広大な放牧地にアクセスできなくなり、トナカイ飼育者はトナカイが生き残るために餌を買わざるを得なくなっている。多くの牧畜民は、破産から逃れるために伝統的な生計を放棄せざるを得なくなり、そのような極度のプレッシャーの一環として生まれたメンタルヘルスの蔓延が、特に若い牧畜民の間で深刻になっている。スンナさんは、トナカイ放牧に対するスウェーデン政府の取り組みを「友達と一緒に車を運転するのに、友達が免許を持っていないのに、どう運転すべきか決めている」ようなものだと例えている。
実際、グリーン経済を構築しようとする主張と、その過程で先住民サーミ人の知識を無視しているとされる取り組みは、緩和すると主張する問題そのものを悪化させ、そこに住む土地、動物、人々に害を与えているとフョードロフ氏は主張する。
フョードロフの仕事の重要なテーマの中には、風力発電所の建設のためであれ、木材や製紙の生産のためであれ、サーミ森林の産業伐採が含まれます。その結果として生じる土壌侵食と洪水により、沈泥が川に流れ込み、土砂の負荷が増加し、その結果、川の生物多様性と魚の個体数が減少します。トナカイは、不可欠な食料となる樹木地衣類の量が減少することによってさらに影響を受けます。特に冬には、雪が降って食料源として地上地衣類にアクセスできなくなります。フョードロフさんは森で話しながら、態度や理解の激しい衝突を嘆いた。「彼ら(政府や企業)にとって、それは商品ですが、私たちにとって、それは文化の核心なのです」と彼女は言う。
Duodji: 創造性が生まれる哲学
この衝突は、芸術実践における大きく異なる概念にも現れています。特に、「芸術」を意味する北サーミ語 (「ダイダ」) が 1970 年代になって初めて発明されたという事実によって例示されています。この用語集への追加は、サーミ人の不可欠な概念である「ドゥオジ」が西洋芸術の分野で頻繁に誤訳されるため、サーミ人の美学が「工芸品」として無視されずに認識されるようにすることを目的としていました。
創造的な活動の記述子であり、西洋の芸術概念よりもはるかに範囲が広いメタカテゴリーであるドゥオジは、サーミ人コミュニティの「知識空間であり、主導的な認識論」であるとガルシア=アントンは言う。
この知識空間には、精神的な思考、土地や水とのコミュニケーション、倫理、そして世代から世代へと受け継がれ、物の製作に収束する美と有用性の概念が含まれています。土地が人々と不可分であるように、総合的なサーミの世界観では、創造性と美も人生の他の要素と不可分です。 「必要とされるものだけを作り、世にもたらすだけです。『精神的な』ものと『物質的な』ものの間にはそのような区別はありませんが、この 2 つは絡み合っています」とフョードロフ氏は説明します。この哲学の重要な要素は、サラの最も有名な作品が示すように、トナカイの頭蓋骨や死骸など、自分の世界にあるあらゆるものを利用することです。 「[サーミ館]がやろうとしていることの1つは、ドゥオジを復活させ、それをサーミの哲学的観点として再評価することです」とガルシア=アントンは言う。
サーミ館のアーティスト紹介
マレット・アン・サラ
サプミのノルウェー側、グォブダゲアイドゥヌ (カウトケイノ) に拠点を置くマレット アンネ サラ (1983 年生まれ) は、トナカイ飼育者の家族に属しています。彼女の作品は、トナカイ遊牧民が経験したトラウマを中心に、植民地時代の構造の中でサーミ人の世界観と伝統的な生活様式を維持するための闘争を探求しています。
彼女の最も有名な作品、Pile o'Sápmi は、ドクメンタ14サラが「200頭の血まみれのトナカイの頭が助けを求める世界への呼びかけだ」と表現したこの記念碑的なトナカイの頭蓋骨の彫刻は、サラが進行中のアートプロジェクトと同名の抗議運動の一部を形成している。
ノルウェー政府によるトナカイの強制屠殺に対する抗議であり、サーミ人の生活を積極的に損なう政策に対する広範な挑戦でもあるこのパイル・オサプミは、非常に個人的なものでもある。オスロ国会議事堂の前に吊るされたトナカイの頭蓋骨のカーテンなど、作品を繰り返しながら、パイル・オサプミは、芸術家の弟の闘いに注目を集めています。生活を維持するための法廷闘争あまりにも大幅に群れを淘汰する命令を受けたため、彼は破産の危機に瀕した。ノルウェー政府による度重なる控訴の末、兄が最終的に敗訴したため、サラは自分の仕事を「公開裁判、失敗した社会の裁判」と考えている。
サラのヴェネツィアでの作品は、彼女の芸術活動の新たな段階を表しています。「ドクメンタでの私の仕事が、この北欧植民地主義の大混乱に取り組み、可視化することであったとしたら、ヴェネツィアはその余波です」と彼女は言います。詳細は明かさないが、植民地時代の建造物によって負ったトラウマを癒し、サーミ人の知識と精神的価値観を前面に押し出す作品を作ることに焦点を当てていることをほのめかした。特に、彼女の考えは、環境の刺激や感情が処理される準備段階として、胃を介した周囲の世界との非言語コミュニケーションに焦点を当てています。
アンダース・スンナ
「6歳のとき、アーティストになってトナカイ飼いになると決心しました。アーティストのアイデアのほうがうまくいきました」とアンダース・スンナさん(1985年生まれ)は、サープミのスウェーデン側にあるヤーコーモーケ(ヨックモック)のスタジオに立って笑います。
彼は現在、自分自身を「ゲリラのトナカイ遊牧民」と呼んでおり、先祖代々の土地とトナカイ牧畜のマークを使用する家族の権利はスウェーデン国家によって非合法化されている。スンナの政治的色彩を帯びた絵画、壁画、音響インスタレーション、詩などの芸術は、森林でのトナカイ飼育を守るための彼の家族の闘いを証明しています。
ヴェネツィアでの彼のプロジェクトは、法廷文書のライブラリーを収めたキャビネットに収められた大規模な絵画を通して、スウェーデン当局との50年にわたる法廷闘争を語ることになる。過去と現在の闘争を認識しながら、スンナの作品は、将来の世代への癒しと力を与えるパイプとして機能します。 「このプロジェクトはすべて家族で作り上げたものです」とスンナさんは説明します。「兄弟が一緒にヴェネツィアに来てくれるだけでなく、小さな息子が法的書類のコピーを手伝ってくれたり、子供たち二人が荷物の整理を手伝ってくれたりしています。」
パウリナ・フョードロフ
パウリナ・フョードロフ (1977 年生まれ) は、スコルト・サーミ人のアーティスト、劇場監督、映画製作者、土地保護者 (サーミ人の視点から情報を得た自然保護活動家) です。彼女の家族はトナカイ飼育者で、もともとサプミのロシア領であるコラ半島の出身だったが、1944年のロシア国境の引き直しに伴い移住を余儀なくされた。北欧サーミ評議会そして、その任務の共同起草を行った。フィンランドの真実和解委員会 i2019年、フョードロフは現在、産業による森林伐採とそれがサーミの土地と水域に及ぼす影響、さらにはサーミ社会を支える集団的な生存モデルと環境保護のモデルを解体する政府の政策と消費主義の責任に焦点を当てている。
NGOと協力した実践的な森林と河川の再生プログラムを含む彼女の実践雪変化は、植民地時代の構造によって課せられた抑圧的な生き方や考え方からサーミ人の身体と心を解放することを目指しています。土地の守護、その土地における先住民族の生き方、パフォーマンス、演劇をひとつにまとめたフョードロフのヴェネツィアでの仕事は、「より広範なプロジェクトの出発点」であると彼女は言う。
「私はすべての損失を記録することに人生を費やしてきた[…]今は、私たちがまだ持っているものとそれをどう強化するかに焦点を当てることが重要だ」。彼女の 3 部構成のパフォーマンス『Matriarchy』(「オークション」と題されている)の第 2 セクションでは、象徴的に風景が「オークション」にかけられる、サーミ パビリオンでのより広範なプレゼンテーションに言及しています。
ビデオスクリーンには風景のフィルムが上映され、訪問者は入札してフョードロフと相互契約を結ぶことができます。買主はポートレートビデオと事前に取り決めた風景を訪れる権利を購入し、その収益でフョードロフ氏はスノーチェンジと協力してその土地を買い戻してサーミ人保護し、保存と復元を誓約することになる。
「私たちのメッセージはこれです」とフョードロフ氏は言う。「私たちの土地を買わないでください。代わりに私たちのアートを買ってください。」
ビエンナーレ アルテ 2022 は 4 月 23 日にヴェネツィアで開幕し、2022 年 11 月 27 日まで開催されます。