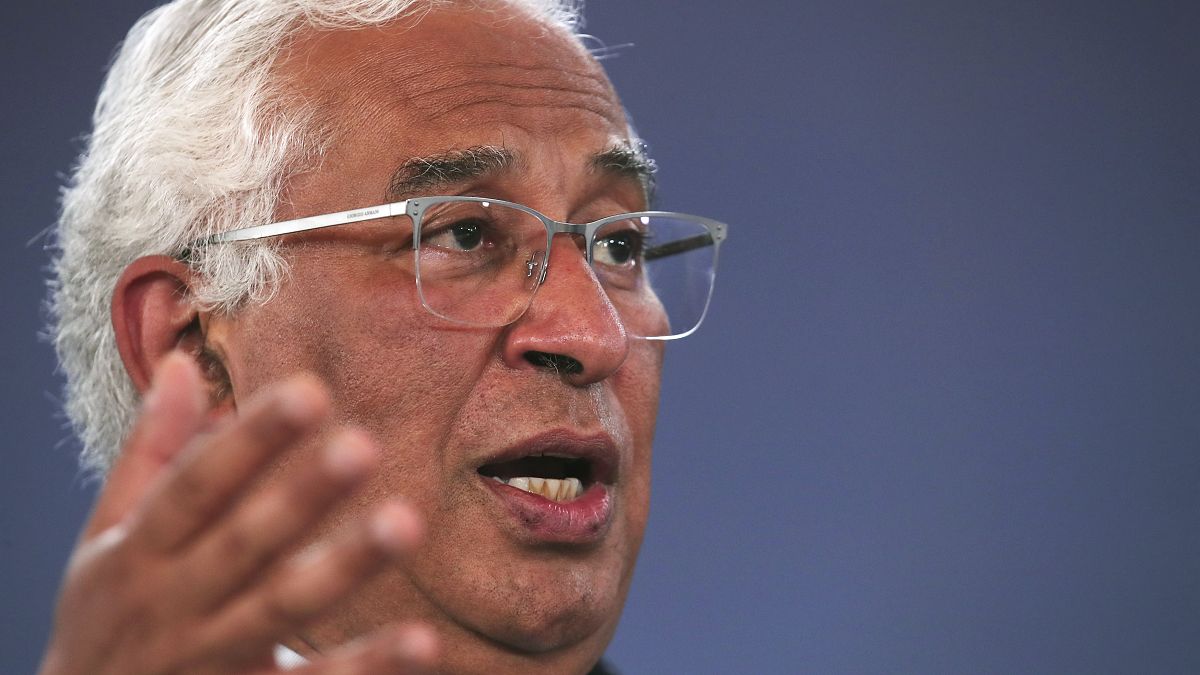富裕7カ国(G7)のエネルギー・環境大臣らは日曜日、日本の北部都市での2日間の協議を終え、よりクリーンな再生可能エネルギーへの移行を加速するよう取り組むと誓ったが、石炭火力発電所を段階的に廃止する日程は設定しなかった。札幌。
当局者らは、5月に広島で開催されるG7サミットに先立って、自らの約束をまとめた36ページのコミュニケを発表した。
日本は、エネルギー安全保障を確保するために、いわゆるクリーンな石炭、水素、原子力エネルギーを強調する独自の国家戦略について、他のG7諸国から支持を獲得した。
「現在の世界的なエネルギー危機と経済混乱を認識し、我々は遅くとも2050年までに温室効果ガス(GHG)排出量実質ゼロへのクリーンエネルギーへの移行を加速するというコミットメントを再確認する」とコミュニケにはある。
首脳らは、炭素排出量を早急に削減し、2035年までに「大部分が脱炭素化された電力部門」を達成する必要性を改めて強調した。
「私たちはクリーンエネルギーへの移行を公正な方法で加速するために、世界中で止まらない新たな石炭火力発電プロジェクトをできるだけ早く中止するよう他国に呼びかけ、また協力していく」と文書には書かれている。
2035年までに各国が「大部分」クリーンエネルギーに依存するという規定により、化石燃料火力発電を継続する余地が残されている。しかし、閣僚は、排出量を回収して大気中への流出を防ぐ仕組みを採用していない「止まらない」石炭火力発電の段階的廃止に向けた措置を優先することで合意した。
ジョン・ケリー米国大統領気候担当特別特使は、今回の会談は「非常に建設的だった」と述べた。
ケリー氏はAP通信とのインタビューで、「化石燃料を段階的に廃止するという目標に向けた団結が表明されたことは、非常に重要な声明だと思う」と語った。
エネルギー市場の混乱
この行動喚起は、ロシアの対ウクライナ戦争による混乱のさなか、中国やその他の発展途上国が化石燃料の段階的廃止とエネルギー価格と供給の安定化に向けたさらなる支援の要求を強めている中で行われた。
石炭火力発電所を段階的に廃止するためのスケジュール設定の問題は、長年の懸案事項である。日本は発電量の3分の1近くを石炭に依存しており、炭素排出を回収する技術を利用して、燃料として使用すると水しか生成しない水素を生成する、いわゆるクリーンコールの利用も推進している。
G7 諸国は世界の経済活動の 40%、世界の炭素排出量の 4 分の 1 を占めています。彼らの行動は重要ですが、気候変動の影響を緩和するための資源がほとんどなく、気候変動の最悪の影響に苦しむことが多い裕福ではない国々への支援も重要です。
先進国の排出量は減少しているが、歴史的には排出量のほうが多く、米国だけで歴史的な世界の炭素排出量の約4分の1を占めているが、新興市場国と発展途上国は現在、世界の炭素排出量の3分の2以上を占めている。
グローバル・サウスへの財政支援
札幌での会議にも出席していた次回の国連気候変動枠組会議(COP28)の議長候補は、G7諸国に対し、途上国のクリーンエネルギーへの移行に対する財政支援を増やすよう求める声明を発表した。
アル・ジャベル国王は、仲間の指導者に対し、気候変動の影響を緩和し、適応し、特に発展途上国における生物多様性の保護を支援する取り組みを促進するため、気候変動資金に関する「新たな取引」の実現に協力するよう求めた。
「私たちはグローバル・サウスのために、より公平な取引をしなければなりません。最も必要とする人々や場所に届けることが十分ではありません。」と彼は言いました。
同氏は、先進国は2009年のCOP15会議で行った1000億ドルの約束を履行する必要があると述べた。次回の協議は11月下旬にドバイで開催される予定。
中国の習近平国家主席とブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダシルバ大統領は共同声明を発表し、「先進国から提供される資金が年間1000億ドルの約束を下回り続けていることを引き続き非常に懸念している」と述べた。
ルラ氏は金曜日、北京で習氏と会談した。
インドのブペンダー・ヤダブ環境大臣は、経済発展が気候変動に対する最初の防御であるとツイートで述べた。
「2050年までに実質ゼロに到達するという世界目標には、先進国による排出量削減の強化が必要だ」とヤダブ氏は述べ、インドのような国々が経済発展する余地を与えることが、気候変動、環境悪化、汚染の影響に対する最善の防御策であると述べた。 」
異なるエネルギー戦略
札幌で作成された文書には、G7のエネルギー戦略間の相違を考慮するためのかなりのニュアンスが含まれていた、と気候変動擁護団体は述べた。
「彼らは気候危機への対応の緊急性について大胆な言葉を発しているが、本当の試金石は、彼らが野心を拡大するという公約について世界の他の国々に何を語るのかということだ」と気候変動対策会社E3Gの上級アソシエイト、アルデン・マイヤー氏は語る。とシンクタンクはコミュニケ発表直後のツイッタースペースセッションで述べた。
しかし、他のG7諸国が日本が化石燃料の利用拡大を認める抜け穴を拡大するのを阻止した一方で、その約束は「必要とされていた明確な行動喚起には及ばない」とマイヤー氏は述べた。
G7のエネルギー・環境相が札幌で会合を終えている間、さらに南の山間部の都市軽井沢ではG7の外相らが地域の安全保障やウクライナ戦争など他の共通の懸案に取り組んでいた。
戦争により、石油とガスの貿易が混乱し、価格が急激に上昇することで、再生可能エネルギーへの切り替えに向けた取り組みが複雑化している。そして、さまざまな理由からそれを終わらせなければなりません。
ケリー氏は「これは正気の沙汰ではなく悲劇だ」と述べたが、二酸化炭素排出量の段階的削減は続けられるし、続けなければならない。
ケリー氏はドイツの再生可能エネルギー導入の進展を指摘し、「場合によってはエネルギー安全保障が誇張されていると思う」と述べた。