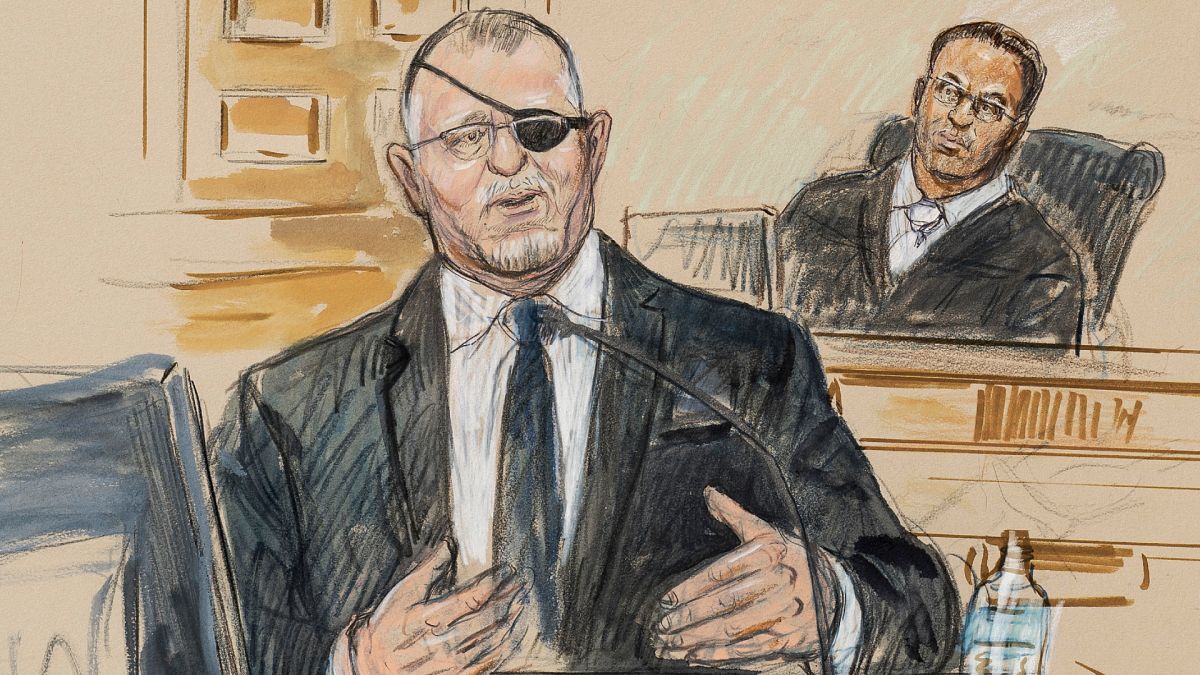ヨーロッパの博物館には、植民地時代にアフリカ、南米、アジア諸国から押収または略奪された工芸品が溢れています。
大英博物館は現在、そのウェブサイトに「争われたオブジェクトベナンのブロンズ像や、イースター島の大きな石のモアイ 2 個のようなものです。
池の向こう側でも、アメリカ先住民の工芸品の展示をめぐる状況も同様に論争を巻き起こしている。
1990 年の連邦政府によるネイティブ アメリカン墓保護および本国送還法に基づいて返還されるはずだった数十万点の品物が、今も博物館に保管されたままです。
ネイティブアメリカンの部族は今も米国の博物館からの品物を待っている
アメリカ自然史博物館の広大なネイティブ アメリカン ホールの中に、かつてマンハッタンを領土としていた部族の間で神聖な場所を占めている小さな木製の人形がひっそりと展示されています。
博物館やその他の博物館が全国的に展示物を板張りしたり紙で覆ったりする劇的な措置を講じて以来、半年以上にわたり、儀式用のオータス、つまり人形存在は視界から隠されている。
この措置は、各機関が神聖な品物や文化的に重要な品物を部族に返還するか、少なくとも展示や研究について同意を得ることが義務付けられた新しい連邦規則に対応して行われた。
博物館関係者は、要件を遵守するために1,800点以上の品目を見直していると同時に、半世紀以上前の展示品の大規模な見直しも視野に入れている。
しかし一部の部族指導者らは、博物館の対応が十分迅速ではないと主張し、依然として懐疑的だ。
結局のところ、この新しい規則は、1990 年の連邦政府のアメリカ先住民墓保護および本国送還法に基づいて返還されるべき数十万点の品物が博物館の管理下にあるという部族からの長年の苦情によって引き起こされた。
マンハッタン在住で、400年以上前にヨーロッパの商人が出会ったレナペ族の子孫であるインディアンのデラウェア族の一員であるジョー・ベイカー氏は、「物事の動きが遅いなら、それに対処してください」と語った。
「コレクションは私たちの物語の一部であり、私たちの家族の一部です。私たちはそれらを家に持ち帰る必要があります。私たちはそれらを近くに置く必要があります。」
ニューヨーク博物館のショーン・ディケーター館長は、部族は間もなく当局からの意見を聞くと約束した。同氏は、スタッフがここ数カ月間、部族コミュニティとの連絡を開始するために展示品を再調査していると述べた。
「最終的な目標は、ストーリーを正しく伝えることです」と彼は語った。
博物館関係者らによると、オタ族をめぐる部族代表者らとの協議は2021年に始まり、今後も継続されるが、この人形は米国外の部族であるマンシー・デラウェア族に関連しているため、実際にはアメリカ先住民の墓保護・本国送還法の対象にはならないが、カナダのオンタリオ州にある国。
同博物館はまた、秋にはアメリカ先住民の声を取り入れ、閉鎖されたホールの歴史、変更が加えられた理由、そして将来がどうなるのかを説明する小さな展示を開く予定であると同氏は語った。
ニューヨークのハンプトンにある連邦政府公認の部族、シャインコック・インディアン・ネイションの副会長ランス・ガムズ氏は、展示会の閉鎖が数年に及ぶ可能性があり、公共機関で地元部族の代表が失われることを懸念していると述べた。
「部族は博物館から私たちの歴史を書き残されることを望んでいないのではないかと思います」とガムズ氏は語った。 「文字通り墓場から盗まれた工芸品を使うよりも良い方法があるはずです。」
博物館は略奪品のデジタルレプリカを展示できるかもしれない
一部の博物館では、ネイティブ アメリカンの展示品の表示を更新する措置を講じています。
シカゴのフィールド博物館は、古代アメリカと北西部沿岸と北極の人々をテーマにした館内でいくつかの事件を隠蔽した後、本国送還センターを設立した。
同博物館は過去6か月間に約40点の品物を含む部族への4件の本国送還を完了しており、追加の品物を含む少なくともあと3件の本国送還が保留中である。フィールド博物館の広報担当者ブリジット・ラッセル氏によると、これらの送還は、新しい規制が適用される前から進められていた取り組みによるものだという。
同博物館の広報担当者トッド・メセク氏によると、オハイオ州のクリーブランド博物館では、アラスカ州のトリンギット族の遺物を展示するケースが、指導者の同意を得て再開されたという。
シャイアン族とアラパホ族の言語文化部門を率いるゴードン・イエローマン氏は、博物館はよりデジタルでバーチャルな展示を行うよう努めるべきだと語った。
これはヨーロッパの博物館にとっても解決策となる可能性があります。技術の進歩により、オリジナルの素材を使用するなど、ほぼ同一のレプリカが簡単に作成できるようになります。
「理論的にはレプリカを作成できるため、盗まれた工芸品のさらなる送還が可能になるはずです」とエリザ・ビア氏は学生新聞『ジャスティス』に書いている。
「ほぼ正確なレプリカが作成できるのであれば、なぜ博物館はオリジナルの品物を保管し続けるのでしょうか?さらに言えば、デジタル レプリカが作成できるのに、なぜ物理レプリカを作成する必要があるのでしょうか?」