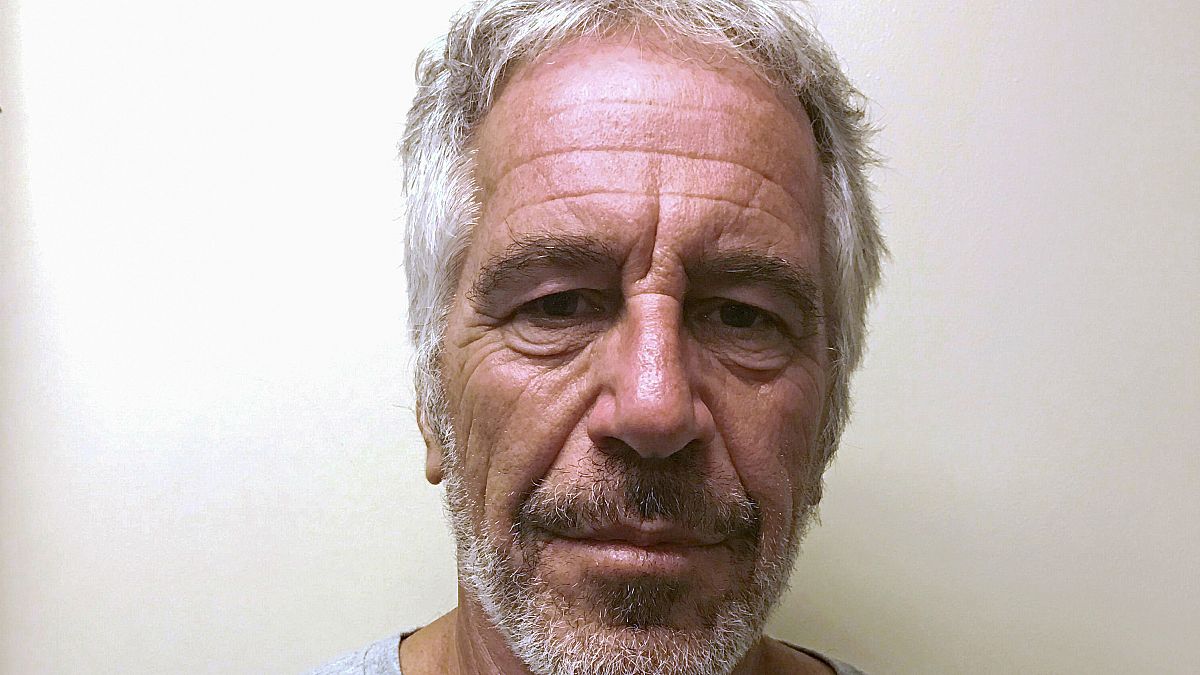公開日
この記事をシェアする
このイライラするほど目的のないロードムービーは、遺伝性のトラウマとホロコーストの遺産を掘り下げようとしています。その善意の努力は、主人公を完全に耐えられないものにする脚本によって台無しにされます。
ドイツの監督ジュリア・フォン・ハインツがオーストラリアの小説家リリー・ブレットの半自伝的小説「Too Many Men」を映画化すると発表されたとき、興奮するのには十分な理由がありました。
ヴェネツィア初公開の『アンティファ』スリラー映画から脱却そして明日は全世界が(そして明日は全世界が)、フォン・ハインツは、ブレットの小説に理想的に合っているように思えた。この小説は、アメリカ人実業家ルースが、アウシュヴィッツ生存者の父親エデクをポーランドに連れて行き、未来とよりよく向き合うために過去と向き合う様子を描いた、感動的で洞察力に富み、しばしば滑稽な物語である。 。 1999 年の本は、遺伝性のトラウマと、ホロコーストの遺産が世代を超えてどのように経験 (または誤った経験) されているかを扱う歴史の思慮深い発掘として位置づけられています。フォン・ハインツは両方の作品で探求したものです。ハンナの旅そしてそして明日は全世界が。
ブレットの物語を大画面で上映したことですべてが水泡に帰し、原作が忘れられないほど正確でありながら悲劇的なほど普遍的なものとなったものを見事に捉え損ねているのは、何と残念なことだろう。それ以上に、宝物この本はイライラするほど目的がなく、時には不快感を与えるため、ブレットの本を読んだことがない人は本を探す気を失ってしまうかもしれません。
そのような偉業を達成した映画は失敗としか考えられません。
宝物主演のスティーヴン・フライとレナ・ダナムは、1991年にアウシュヴィッツへの人生を変えるロードトリップに乗り出す父と娘のペアを演じる。鉄のカーテンは下りた。つまり、亡命ユダヤ人は帰還して自分たちの歴史と再びつながる可能性がある。二人の口論のやり取りは、二人ともスペクトルの反対側からこの帰国に直面しているという事実を捉えています。エデクは愛想の良い本性でトラウマを隠しているが、ルースは最近の離婚と母親の死を受けて、新たな目的意識を見つけたいという願望に向かって全力で取り組んでいる。
不一致のキャラクターの間で確立された行き来、役のためにポーランド語を学んだフライの称賛に値する献身、そして俳優が感情的になったときにドライアイを維持するのは不可能であるという事実以外には、実際には大したことはありません。宝物それは真実に聞こえます。これには多くの理由がありますが、最初はありきたりな会話ですが、全体を通しての 1 つの大きな障害は、ルースの性格です。
確かに、彼女は好感の持てるキャラクターである必要はありませんが、ルースの不安の部分に焦点を当てている場合でも、ダナムと脚本は彼女を複雑にしたり、徐々に同情させたりすることは決してできません。本当に迷惑なだけです。
彼女は音痴で不快なアメリカ人の典型で、ポーランド人に「メ・ラモ・ルース」と素っ気なく挨拶しないと「私は英語が話せません」と叫ぶ。このキャラクターが実業家からジャーナリストにキャリアを変えたことを考えると、最低限のリサーチをしたり、生きていくためにいくつかの常套句を学んだりすることができたはずだと敢えて考える人もいるかもしれない。そして、アウシュヴィッツを博物館と呼んだ人々を彼女が叱るとき(「それは博物館ではありません。死の収容所です!」)、彼女の心が正しい場所にあるかもしれないと認めて疑いを有利に運ぶのは難しいです。あなたはただ、トラウマを無神経に利用したとして彼女を叫びたいだけであり、英語が母国語ではない人々はアウシュヴィッツが何であるかを表現する適切な用語を持っていない可能性があることを理解していないことを非難したいだけです。
脚本はダナムの性格と常同的な神経症に焦点を当てすぎており、彼女が治らないほど自己中心的で成長できない人物として描かれているため、これらはすべてダナムの責任ではありません。無神経に電車の切符を予約するという最初の失敗から、映画の終盤での涙目での非難まで、ルースは、PTSDに苦しんでいるのは自分だけではないかもしれないということを理解できない。たとえそれが重要な点であっても、ブレットの本は悪びれない主人公に私たちの注意を引くことに成功しているが、脚本はこれについて、あるいは人間がいかに複雑でユニークで素晴らしい矛盾の塊であるかについては決してコメントしていない。また、生き残るという行為が過去を葬り去りたいという願望に変換される、相容れない世界の経験を特徴とする世代間の溝を意味のある形で掘り下げているわけでもない。この映画がやっているのはルースをさらに非感情的にすることだけで、今年これほど耐え難いキャラクターを見つけるのは難しいほどだ。
いかなる状況でも賄賂を受け取ることができる泥棒に堕落したポーランド国民の描写については、あまり語られないほど良い。
欠点に対して真剣に、宝物『追悼の旅』は、最終的には奇抜な不発に終わり、もっと評価されるべき小説の価値を過小評価するものとなった。
宝物は今出ています。